 パリ日本文化会館で、「アジアのキュビズム」という展覧会が開かれている(5月16日~7月7日)。20世紀初頭、ヨーロッパで生まれた美術様式の一つであるキュビズムが、アジア各国でどのように受け入れられ、また受け入れられなかったかを検証する展覧会である。アジア11カ国より、53人の作家、合計77点がパリに送られて、現在展示されている。しかしここに、今回の展覧会に出品されそこなった1枚の絵がある。フィリピンを代表する作家、キュビズムの第一人者といわれているヴィセンテ・マナンサラの「スラムのマドンナ」という作品だ。
パリ日本文化会館で、「アジアのキュビズム」という展覧会が開かれている(5月16日~7月7日)。20世紀初頭、ヨーロッパで生まれた美術様式の一つであるキュビズムが、アジア各国でどのように受け入れられ、また受け入れられなかったかを検証する展覧会である。アジア11カ国より、53人の作家、合計77点がパリに送られて、現在展示されている。しかしここに、今回の展覧会に出品されそこなった1枚の絵がある。フィリピンを代表する作家、キュビズムの第一人者といわれているヴィセンテ・マナンサラの「スラムのマドンナ」という作品だ。この作品は先の東京、韓国、シンガポール展の際にも展示されず、カタログに図版入りで紹介された(ちなみにパリ展のカタログにも登場している)。今回は、早々にパリ展の作品候補リストに入り、その出品交渉をわれわれマニラ事務所スタッフが行うことになった。実はこの絵、私も初めて図版を見たときに、一遍でぐっと惹きつけられた作品で、なんとか出展を承諾してもらうべく、オーナーに何度も電話をかけ、やっとのことで面談の約束を取り付け、直談判ではありったけの言葉でこの作品の素晴らしさと、今回の展覧会でいかに重要な位置づけであるかを強調した。かなりしつこいまでにねばったのだが、結局よい回答が得られず、最終的に出展はかなわなかった。
マナンサラは、間違いなくフィリピンの美術史における最重要の作家の一人で、1910年生まれで1981年に亡くなるまで、独自のキュビズムのようなスタイルを中心に多くの作品を残した。今回のパリ展でも、「スラムのマドンナ」にはふられたが、彼の別の作品が3点(「コラージュ」(1969年)、「磔刑」(1971年)、「ヌード」(1973年))も展示されている。その彼が人生の半ば、40才に達した1950年に描いたのが、この作品だ。当時彼は、フィリピン人として戦後初めてユネスコの奨学金を得て、カナダに6ヶ月間滞在した。そして一旦帰国した後、今度はパリへ留学して、レジェという作家に師事して本場のキュビズムに出会うこととなった。この作品は、そうした海外渡航の合間に描かれたもので、その後の彼の進路を暗示する重要な作品となった。
以前このブログでも触れたことがあるが、フィリピンにおけるアカデミズム画檀の歴史は意外と古い。スペインの植民地時代、エリート教育の一環として絵画が導入され、何人ものフィリピン人が画学生として西洋に渡ったが、その中で、ホアン・ルナとフェリクッス・ヒダルゴという二人の作家が頭角を現し、1884年には二人そろってマドリッドのサロンで金賞と銀賞を受賞するという象徴的なできごとがあった。1884年当時の日本といえば、西洋画の基礎を築いたと言われている黒田清輝が、18歳で初めてパリに渡った年。日本洋画壇のアカデミズムを牽引することになる“外光派”が成立するには、さらに10年を要した。その頃フィリピンには、既に西欧の本場サロンで認められる作家が複数いたということが、この国におけるアカデミズムの早熟ぶりをうかがわせる。ちなみにこの時代の作品の多くは、今でもシンガポールや香港のオークションにかかり高値で売買されていて、2002年には政府系のGovernment Service Insurance System(いわゆる日本でいま話題の“社会保険庁”にあたる)が、ホアン・ルナの「パリジャンの生活」(1892年)を、4600万ペソ(約1億円)で競り落として購入したことが話題となった。どこの国でも、この社会保険を財源とする金は不透明極まりなく、行き場所にも困っているようだ。
 ホアン・ルナ作「スポラリウム(略奪)」(1884年)
ホアン・ルナ作「スポラリウム(略奪)」(1884年)さてそんな強固なアカデミズムに対抗し、第二次大戦前あたりから反旗を翻したのが、 “サーティーン・モダーンズ”と呼ばれる13人のアーティストたちで、マナンサラはその一人と位置づけられている。
そしてこの「スラムのマドンナ」だが、今回の展覧会の出品候補リストに載せられたのは、私が考えるところ二つの理由があると思う。一つはカソリックが主流を占めるこの国で、繰り返し描かれる母子像がテーマとなっているから。その姿は当然、幼子(おさなご)キリストとマリアの聖母子像にだぶる。展覧会場となるパリは無論キリスト教文明圏で、誰もが容易に解釈ができ、その文脈を理解(誤解)することのできる図象だからであろう。さらにもう一つ、それはおそらくスラムという表象が持つ、ある意味わかりやすいアジアのイメージによるものだろう。廃墟のようなバラック小屋の建て込むスラムの前で、幼児をすっくと抱いて、怒りや不安の中にも毅然と胸をはる若い母親。こうした二つのイメージの交差するこの作品は、今回の展覧会のモチーフを明瞭に象徴する。“悲しき熱帯”であるフィリピンに、キリスト教という西洋文明が移植された図は、あたかもキュビズムという西洋美術の技法が、土着の文化に移植された姿と二重写しになるだろう。
でも、私がこの絵から感じるものは、そうした観念的なことではなかった。この絵の中に潜む強靭さ、そして不気味にも不屈な眼差しは、一体どこから生まれたのだろう。そして、自分自身、どうしてこんなにまでこの絵のことが、心のどこかにひっかかるのだろうか・・・いろいろ調べているうちに、あることが気になり始めた。
この絵が描かれたのは1950年。マナンサラの作風に決定的な影響を与えたといわれる太平洋戦争の終結から5年後のことである。マニラで生まれ育った彼は、日本軍の侵攻後、北部の田舎に疎開をしていた。戦争終結とともに再びマニラに戻って見たものは、その後の彼の創作人生を決定付ける光景だった。破壊され尽くし荒廃したマニラの街。それ以来、彼は麗しき自然描写をいっさい放棄したという。
「1945年2月3日にサント・トーマス大学の民間人収容所解放に始まったマニラ解放戦は、翌3月3日をもって日本軍が完全に掃討されるまで約1ヶ月にわたり続いた。この間にマニラ市街は文字通り廃墟と化し、日本軍守備隊約2万名はほぼ全滅、米軍も約7千名の犠牲者を出した。しかしなんと言ってもマニラ戦最大の犠牲者は、約10万にのぼると言われる非戦闘員・民間人であった。その恐らく7割が日本軍による殺戮と残虐行為の犠牲者、残り3割が米軍の重砲火による犠牲者だとされる。このように第2次世界大戦でワルシャワに次ぐ都市の破壊と言われ、また日米間で戦われた初めての、また最大の市街戦であったマニラ戦は、その結果の悲惨さゆえに、解放戦であると同時に「マニラの破壊」あるいは「マニラの死」とも呼ばれている。」
(中野聡・一橋大学教授のホームページより、「戦争の記憶」に関する同氏のホームページは、多くの示唆を与えてくれる。)
「マニラの虐殺」ともいわれ、今も語り継がれている惨事だ。マニラの旧市街には、「非戦闘員犠牲者(non-combatant victims)」10万人を追悼する祈念碑が立ち、いまも毎年2月に追悼式が行われている。その出来事は繰り返し繰り返し、フィリピン人の間で語り継がれていて、私がこの国に赴任した2005年にも、「Terror in Manila」(メモラ-レ・マニラ1945財団)という本が新たに出版された。60年以上を経た今日でもいまだ呼び覚まされている記憶。戦後5年という時間は、凄惨な「マニラの死」から癒されるには全く不十分な月日であったに違いない。この絵に漂うただならぬ怒りと、それを包み込む絶望の先には、廃墟のマニラが広がっていたのではないだろうか。この作品を契機に彼のキュビズム人生が始まるともいえるのだが、私が思うに、彼は彼のその後の人生を決める重要な局面で、5年前のあの廃墟のマニラを思い出していたのではなかろうか。不気味にも不屈な母子像が心のどこかにひっかかるのは、そこに告発の眼差しがあるからだ。
 メモラーレ・マニラ1945記念碑
メモラーレ・マニラ1945記念碑展覧会はある意味、時に残酷だ。絵は見られてこそ価値が生まれ、見られ、消費されることでその絵を巡る物語が作られる。もしもこの「スラムのマドンナ」が海を渡ってパリに行っていたら、どんな物語を我々に示してくれていただろうか。または隠してしまったであろうか。いずれにしても1枚の絵と対峙する時、重要なのは、その絵がこの私に一体何を語りかけるのか、ということだと思う。
「スラムのマドンナ」のオーナーと出品交渉していた時に聞いた話の中で、今でも気になっていることがある。彼女は現在、著名な内科医としてサント・トーマス大学病院に勤めているが、両親は戦前からフィリピン美術のコレクターであった。当時マニラ旧市街にあった倉庫には、マナンサラの戦前の作品をはじめ、多くの美術作品を所蔵していたという。それもあの「マニラの破壊」で灰塵に帰してしまったそうだ。そして、その後調べてみてわかったことだが、母親は国立博物館の美術課長を務めたこともある研究者でまだ健在だが、コレクターであった父親は、1958年に45歳の若さで他界している。その父親だが、終戦後、日本軍の協力者としてフィリピン人民裁判で“売国奴”として有罪となり、4年間も獄中にいたようだ。今回の出品拒否と、ファミリーの戦争体験と、因果関係があるか否かはわからない。しかし、そこにも絵画を巡って、私たちの知る由もない別の物語があるのは確かなことだ。
いまから57年前のマニラで描かれた「スラムのマドンナ」。哀しいことにスラムはいまでもマニラの街の代表的な表象だ。結果的にこの絵に描かれた現実は、今でも同じように生々しく存在している。それは戦争による荒廃ではなく、グローバライゼーションというもの静かな侵略と、腐敗政治による荒廃の中にある。

(了)


















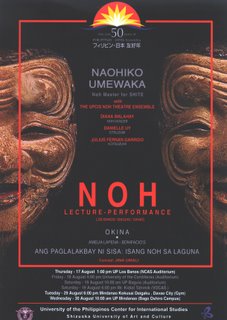







 (写真は全て澤口佳代さん撮影)
(写真は全て澤口佳代さん撮影)




 ボランティアの学生さん
ボランティアの学生さん 
 PETAのワークショップ
PETAのワークショップ




 ミンダナオ国際大学
ミンダナオ国際大学

